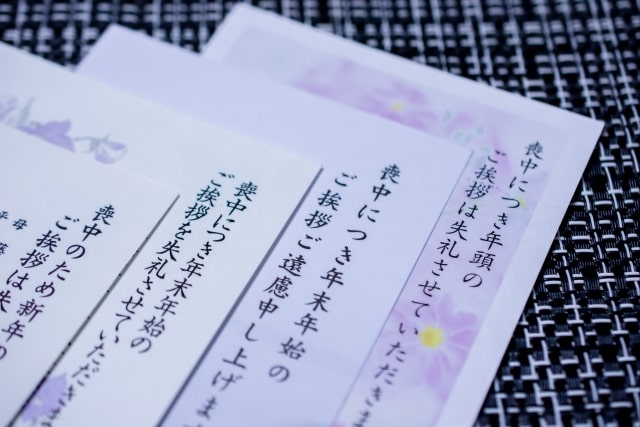喪中はがきの文面で悩むことの一つが、故人の続柄をどう書けばよいのかということですよね。
父とか母なら簡単なのですが、妻や夫の父や母のことはどう書いたらよいのでしょうか。
一般的な呼び方である義父や義母で良いのでしょうか。
ここでは、喪中はがきの文例や、夫や妻の義父や義母の続柄の書き方を解説していきます。
結論から言いますと「義父」「義母」でも構いません。
喪中はがきの文例・義父母が亡くなった場合
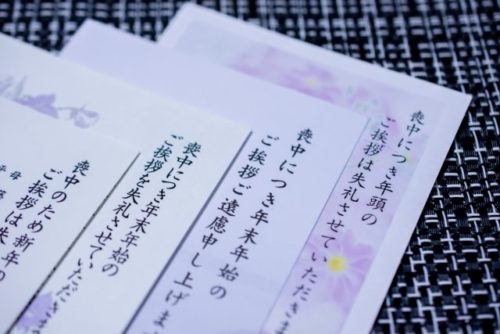
義父や義母が亡くなった時の喪中はがきの文例を紹介します。
喪中はがきを書くときに気をつけるマナーとしては、句読点は使用しない、数字は漢数字で記載する、ということなどです。
基本、縦書きで書きましょう。
義父・義母が亡くなったときの喪中はがきの文例
本年◯月 妻◯◯の父◯◯◯◯が八十歳で永眠いたしました
長年にわたるご厚情に改めて心より御礼申し上げます
皆様が健やかなる新年をお迎えになりますよう心よりお祈り申し上げます
令和〇年〇月
喪中はがきの書き方のポイントは
- 最初に喪中のお知らせや年賀欠礼の挨拶を書きます。
- 他界した日付、年齢、続柄、名前を書きます。
- お世話になったことに対するお礼の言葉を書きます。
- 結びの挨拶や相手への気遣いなどを書きます。
- 喪中はがきを出した日付。差出人の住所氏名を書いてもよいです。
が基本です。
ここでは配偶者の父母の訃報の際の喪中はがきについて解説してますが、祖父母の場合は喪中はがきはどうしたらいいのでしょうか。
例えば妻のおじいちゃんが亡くなった場合などですね。
喪中はがきを出すのかどうか、出すならどう表記するのか意外と知らないものです。
妻の祖父母が亡くなったときの喪中はがきについてこちらの記事にまとめてありますので参考にしてください。
↓↓
喪中はがきは妻の祖父祖母の場合も出す?文例と書き方
喪中はがきの書き方・妻の父と母の続柄

妻の父は一般的に義父と言いますよね。
喪中はがきで記載される場合は、妻の父は「岳父」と表記されることがあります。
ですが、岳父と言われてもピンとこないと思います。
出す方も初めて書くような呼び方ですし、届いた方も普段からあまり目にしないので岳父って誰?ってなるでしょう。
なので「義父」とか「妻の父 〇〇」「妻○○の父△△」と表記しても構いません。
現代ではこの方が分かりやすくて良いかもしれません。
また、夫婦連名で喪中はがきを差し出す場合には、妻の実父・実母であるのにもかかわらず「義父」や「義母」と表記することになります。
実の両親なのに義父・義母と書くのは奥さんにとってはちょっと違和感があるかもしれません。
ですので、「妻○○の父△△」 などと書くのが分かりやすいですし奥さんにとっても違和感がなくて良いと思います。
または、連名とせず夫の名前で喪中はがきを出すと言うのでも良いでしょう。
ちなみに、義父のことは岳父と書きますが、義母のことは丈母と書きます。
妻から見た義父・夫の父の場合
夫から見た妻の両親が亡くなった場合のケースについて説明してきましたが、逆に妻の立場で夫の両親が亡くなった場合はどう書けば良いのでしょうか。
妻から見て夫の父は「義父」になりますよね。
ですが、夫婦連名で差し出す場合は「義父」ではなく「父」と書きます。
妻の義父であっても夫の実父でありますから、「義父」と書くことはありません。
しかし、夫と縁のない妻の友人に喪中はがきを出すとなると妻名義で出すことになりますよね。
この場合は「義父○○」「夫〇〇の父△△」と書くことになります。
喪中はがきを送る際の注意点

喪中はがきというのは「喪中のため新年の挨拶ができません」というお詫びのお知らせです。
このことをしっかりと理解しておきましょう。
喪中はがきを送る相手には、誰に出せばいいのか、どの辺りの交友関係まで送ればいいのかと迷うこともあるかもしれません。
簡単な判別方法としては、毎年年賀状をやりとりしている相手には送れば良いです。
基本的には故人とどれだけ関係が深かったかなど、交友関係を考慮して送るかどうかを決めましょう。
喪中はがきを出す時期は、先方が年賀状を用意する前の時期にしましょう。
つまり11月半ば辺りに出すのが最適です。
先ほども述べましたように、喪中はがきというのは訃報のお知らせです。
淡々と訃報のお知らせと簡単な挨拶を書くだけでいいです。
こちらの近況など余計なことは書かないようにしましょう。
まとめ
配偶者の父母の書き方としては「義父」「義母」のほかに「岳父」「丈母」というのがあると紹介しました。
でも、もっと分かりやすく「妻〇〇の父△△」と書いても構いません。
夫の父母が亡くなった場合、妻が個人名で友人などに喪中はがきを出す場合は、「義父○○」「夫〇〇の父△△」という書き方で構いません。
夫婦連名で出すのか個人で出すのかによっても書き方は変わるので、しっかりと書いて恥をかかないようにしたいものですね。